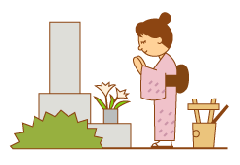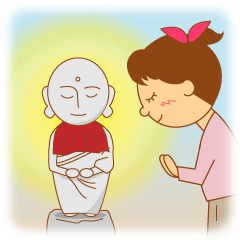一隅を照らす 天台宗
現在のページ:トップページ > 天台宗について - 法話集 > 目次
天台宗について
法話集
No.254お盆に返ってこない御先祖様 ~いつも見守ってくれていることへの感謝を~
 古来、亡くなったご先祖様は年に二度、当家に帰ってくると言われてきました。正月とお盆です。よく「盆と正月が一緒にきたような忙しさ」などと言いますが、これは子どもや孫や親戚が集まって、その接待に忙しいと思っている人が多いかもしれないけれど、本当は御先祖様が大勢お帰りになり、その準備やお供えに大慌てする様子を言った諺です。明治時代以降は神社と仏閣が神仏分離されたために、令和の今日、よくわからない人が多くなりました。
古来、亡くなったご先祖様は年に二度、当家に帰ってくると言われてきました。正月とお盆です。よく「盆と正月が一緒にきたような忙しさ」などと言いますが、これは子どもや孫や親戚が集まって、その接待に忙しいと思っている人が多いかもしれないけれど、本当は御先祖様が大勢お帰りになり、その準備やお供えに大慌てする様子を言った諺です。明治時代以降は神社と仏閣が神仏分離されたために、令和の今日、よくわからない人が多くなりました。お正月には御先祖様は歳徳神(別に年神さま)として恵方から当家に戻られます。その際、当家では門松を立て、注連飾りをして、床の間には鏡餅を供え、神棚を飾ってお迎えをします。現在、節分に恵方巻(巻寿司)を恵方に向かって無言で食べるなどという風習を生んだのも、このことと大きく関わっています。
一方、お盆は御先祖様を精霊として迎えます。地方によって迎える月日も期間もさまざまです。元はお釈迦さまが雨期の間行っていた夏安居が明けた時期に供養を勧められたことが始まりとされ、日本では旧暦7月15日がお盆とされました。これを今の時代に置き換えて、カレンダーどおり7月15日前後に行う場合、月遅れの8月15日前後に行う場合、寺院によってはお檀家の数が多い場合には7月から8月にかけて長期間お盆参りをする場合もあります。1日のことを朔日ということから8月1日を朔盆といいお盆の始まりとする地域や8月7日を七日盆といってお盆の始まる日とする地域もあります。京都では8月13日に六道の辻、六道珍皇寺に御先祖様を迎えに行く風習が今も残ります。こうしてお迎えした御先祖様をおもてなしして、いよいよお送りする日時や方法もさまざまです。有名なのは京都の大文字の送り火ですが、長崎では船を使って精霊流しをしますし、田舎では山や川や海辺などで地域独特の送りの作法が伝わっています。さらに関西では8月24日前後に地蔵盆といって子安地蔵に安産や子どもの成長を願う行事もあります。
さて、長い前置きでしたが、ここからが本題です。亡くなった御先祖様はそんな風に行ったり来たりするのでしょうか?もしそうだとしたら、正月やお盆が済むとこの世からいなくなってしまうのでしょうか?実はそうではないのです。亡くなった御先祖様は見えない大きな大きな姿で私たちの周囲にもあの世にもあらゆる処に存在していらっしゃると考えるべきなのです。小さいお子さんが亡くなったおじいちゃんに「見守っててね!」などというのはまさにおじいちゃんの見守りが可能であるという願いなのです。私たちは亡き御先祖様がいつもどこでも見守って下さっているという安心の中で暮らしていけるのです。
そうすると、正月やお盆に御先祖様を迎える準備や作法を行うことは無意味なことなのでしょうか?そうではありません。私たちは日常の生活の中でいつもいつも御先祖様に対して鄭重な供物や作法を行う訳にはいきません。仕事や娯楽を優先してしまい、仏事をおろそかにすることもあるかもしれません。そんな中で、せめて暦の上での節目だけでもしっかりとお迎えしましょうというのが、正月とお盆に対する大事な考え方だといえます。
御法事も同じです。3回忌、7回忌など御法事の年だから法要して供養させていただきましょうといいますが、本来なら毎年祥月命日がくれば法要なさる方が丁寧です。祥月命日だけでなく、毎月毎月の月命日に行う方が丁寧です。毎日毎朝に供養するのが丁寧に決まっています。
天台宗ではこうしなければならないということはありません。むしろ、檀信徒の皆さんの心持ち、心がけでできるだけのことを精一杯行っていけばよいのです。お正月とお盆はそんな私たちに年に二度、暦の上で御先祖様を迎えてみましょうと示してくれている目安の日ということになるでしょう。
まもなく今年のお盆がやってきます。いつも見守ってくれてありがとう、この時期だけしかお迎えの作法はできないけれど、精一杯お迎えしますね、そんなお気持ちでお盆を迎えてはいかがでしょう!
(文・兵庫教区 真光院 吉田 実盛)
掲載日:2025年08月01日