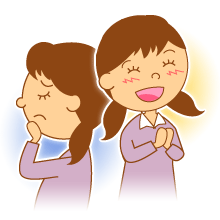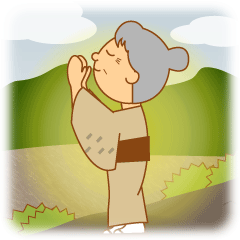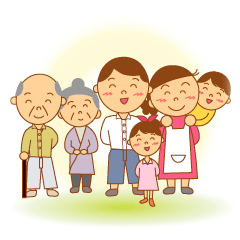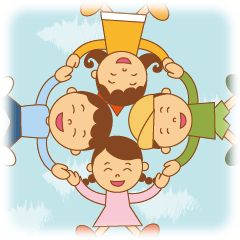一隅を照らす 天台宗
現在のページ:トップページ > 天台宗について - 法話集 > 目次
天台宗について
法話集
No.249歎徳 ご縁が紡ぐ人の善徳
 歎徳とは、他者の美徳をほめたたえる事です。
歎徳とは、他者の美徳をほめたたえる事です。経典の中では諸佛菩薩を敬う場面でよく使われています。
現代では主に葬儀式に於いて、故人の生を受けてからの全ての徳を僧侶が棺前で仏様にお伝えする為の『歎徳文』として用いられています。
云わばその方の人生そのものを語りますので、自分が知っている事のみならず故人とご縁のある方々からもお話を伺います。
何せ長年の徳行を5分程で語る訳ですから、時には何十分もかけてお聴きした内容を数文字の短文で顕したり、様々な方々のエピソードと結びつけ対句にしたりします。
こうして出来上がった歎徳文を読むと、ご家族でさえ知らず忘れていた物事が沢山あり、個々の出来事でも人によって受け方が異なる多辺な側面があることに気付きます。
人の徳というものは、様々な人達とのご縁によって、それぞれが互いに繋がり合っているものだと実感します。
是則ち、善行・徳行とは自分一人だけでは成しえないこと。家族、友人、他者とのご縁を紡ぎ織りあげていくものなのだとも言えるでしょう。
また「歎」の文字は歎(なげく)という意味で使われることもあります。
韓嬰の「風樹の歎」の如く、亡くなられては、これまで受けた恩を返すことができないと歎くこともありますが、故人とのご縁で紡いた善徳を今度は我々が他者へ繋いでいくことが、何よりの恩返しと供養となるのではないでしょうか。
このように歎徳を読みあげる僧侶は、幾多の縁を紡いで徳を為した故人を御導きくださるよう仏様に祈りを込めて文面を読みあげるのが役目です。
歎徳文は仏様に告げる言葉故に難解な言い回しも使われますが、耳を傾け故人と佛と御自身との縁を感じ取り、更に多くの人々へと仏様とのご縁を繋げてくださいませ。
(文・山形教区 聖徳寺 松本 昌順)
掲載日:2025年03月01日