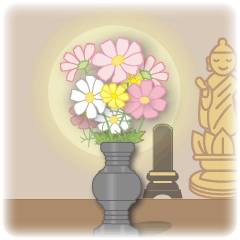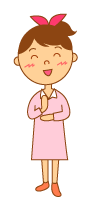一隅を照らす 天台宗
現在のページ:トップページ > 天台宗について - 法話集 > 目次
天台宗について
法話集
No.250感謝とは「感恩報謝」の略なのです
 「感謝」という言葉は感恩報謝の略であると言われています。省略された文字は「恩」、と「報」です。私は略された文字に大きな意味があるのではないかと思います。仏教の法要の表白、法則という日本語でお導師様が宣べられる文章には「抑々、報恩謝徳の場」という言葉が出てきます。「感謝」とは、「恩」に「報」いる、知らず知らずのうちに大変な恩恵を受けたことに「報」いる。徳のある行動であると思います。
「感謝」という言葉は感恩報謝の略であると言われています。省略された文字は「恩」、と「報」です。私は略された文字に大きな意味があるのではないかと思います。仏教の法要の表白、法則という日本語でお導師様が宣べられる文章には「抑々、報恩謝徳の場」という言葉が出てきます。「感謝」とは、「恩」に「報」いる、知らず知らずのうちに大変な恩恵を受けたことに「報」いる。徳のある行動であると思います。さて我々に人生を振りかえって最も恩のある存在、感謝すべき存在はやはり、両親であると思います。母親は腹を痛め我々を生み、仕事を制限し、家事をしながら育て、生きることのほとんどを教えてくれたのではないでしょうか。父親は外で様々な苦労をしながら一家を支えて我が子に苦労をかけまいと、自分を顧みず苦労(苦しい労働の略なのでしょうか)を背負ってくれたのではないでしょうか。
毒親という悲しい言葉もありますが、将来のこと、様々なことで行き違いや、過保護さや、対立もあるかもしれません。しかし人間に生まれてきたことは奇跡的なことであると仏典にも見出すことができます。
雑阿含経に、お釈迦様が阿難尊者に「例えば海の底に目の不自由な亀がいて、その亀が百年に一度、息を吸いに波の上に浮かび上がってくるという。ところが大海原に浮木が漂っていて、その浮木の中ごろに穴が一つだけ空いている。百年に一度浮かぶこの亀が、ちょうどこの浮木の穴から頭を出すことがあるだろうか」とお尋ねになり、阿難尊者は「そんなことは、ほとんど不可能で考えられません」と答えると、お釈迦様は「誰もが、あり得ないと思うが、全くないとは言い切れない。人間に生まれてくるということは、この例えよりも更にあり得ない。とても有難いことなのだ」と仰っておられます。「あり得ない」は、「有り難い」につながります。
そこまで奇跡的なことである人間としての生を過ごすということを感謝無しで過ごすことは「恩」知らずであると思いませんか。感謝することができることが人間として生んでいただいた「恩」を「感」じて「報」いることだとは思いませんか。
最澄様は国宝的人材の育成を生涯の目標として、一隅を照らし、能く行い能く言い、己を忘れて他を利することを示されました。感謝の心が土台となり、最澄様の思いへも「報」いることができると確信いたします。
(文・延暦寺一山 護心院 竹林 幸祥)
掲載日:2025年04月01日