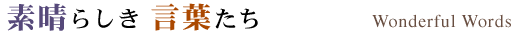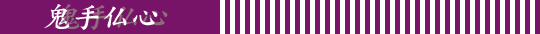能登地震で珠洲市の2カ寺と檀信徒に被害
石川県に義援金寄託
 石川県能登地方で震度6強を観測する地震が5月5日に発生した。
石川県能登地方で震度6強を観測する地震が5月5日に発生した。最大震度を観測した珠洲市には翠雲寺と藥師寺があり、両寺の建物や檀信徒の家屋などに被害が出た。
天台宗では、すぐさま関係各所に被害状況を確認して対応。
一隅を照らす運動総本部では能登地方地震災害義援金を石川県に寄託することを決めた。
天台宗務庁では、地震が発生した5日に、震度が大きかった北陸、信越の両教区の宗務所長に電話連絡し、被害状況の確認と報告書の提出を依頼。報告書の提出を待って対応することを決めた。
珠洲市の翠雲寺(岩尾照尚住職)では、2度の大地震で、本堂と庫裏の屋根瓦が落下。棟瓦にもズレが生じる被害を受けた。
境内の市指定文化財の石塔五重塔、地蔵像2体、墓石10基が倒壊した。本堂と庫裏では6日からの降雨で雨漏りも発生し、室内にも被害が及んだ。
余震による影響も深刻で、10日に発生した地震では、酒井雄哉大阿闍梨謹書の寺号碑も倒壊の危険性が高まっている。
また同市の藥師寺(井上惠照住職)では、ガラスの破損、柱のズレや壁にヒビが入るなどの被害が報告されている。両寺の檀信徒の家屋等でも被害は大きいという。
翠雲寺の岩尾住職は「珠洲市で感じた地震では過去最大の揺れだった」と発生当時を振り返り「今回の地震は本堂内外に大きなダメージを与えるものだった。
翌日の雨で雨漏りも発生し、早急に屋根を仮修繕して対応したが、余震が収まってからの本格的な修理を待たねばならない状態。
檀信徒らは今も地震が続くことや家屋の修繕などへの不安を抱えており、心のケアが必要になってくる」と話している。
一隅を照らす運動総本部では、能登地方地震に対し、緊急救援引当金からの義援金、また地球救援事務局に指定寄付として信越教区仏教青年会と1カ寺から寄せられた約6万円を合わせた106万4855円を5月24日付けで石川県に送金した。
政府の地震調査委員会の報告では、これまでに存在が知られている能登半島の北側にある活断層ではなく、「伏在断層」と呼ばれる地上に現れていない断層や知られていない断層が動いて発生したと説明しており、引き続き注意が必要と呼び掛けている。
天台宗でも、北陸教区宗務所と連携を取りながら被災地の状況を注視していく。
令和5年石川県能登地方を震源とする地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りし、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
天台宗
一隅を照らす運動総本部