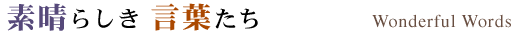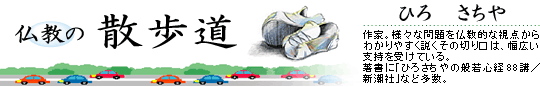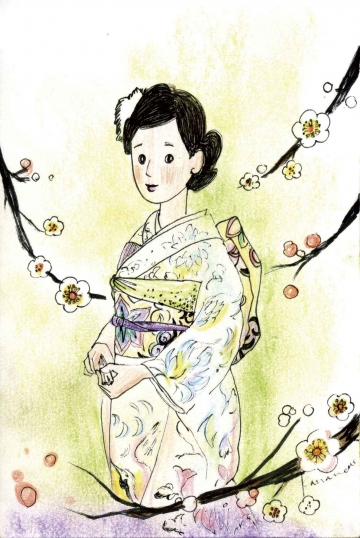インド禅定林開創30周年
大本堂建立10周年記念大法要奉修へ
仏教発祥の地で根付く天台の教え
インド・バンダラ県ポーニ市ルヤード村にある天台宗寺院、禅定林(サンガラトナ・法天・マナケ住職)の開創30周年・大本堂建立10周年記念大法要が来る2月8日に盛大に執り行われる。仏教発祥の地インドに再びその灯火を掲げるべく寺院を建立して以来30年、そしてそのシンボルである大本堂の落慶より10年。以後、サンガ師の努力が実を結び着々と現地に天台宗の教えが弘がっている。今回の記念大法要には、天台座主名代として叡南覺範毘沙門堂門跡門主、サンガ住職の師である堀澤祖門三千院門跡門主をはじめ、天台宗から西郊良光宗機顧問、長山慈信参務、横山照泰参務、中島有淳参務らが、また延暦寺からは小鴨覚俊副執行が出仕・随喜する。禅定林を支えるパンニャ・メッタ協会日本委員会のメンバーである天台宗僧侶ら多数も同じく出仕・随喜する。
 サンガ師は幼少期に来日し、堀澤師の下、比叡山で修行を積んだ。その後、インドに帰国し、ルヤード村で禅定林を主宰。布教活動を続ける一方、大乗仏教精神に基づく社会福祉活動を展開するPMS(パンニャ・メッタ・サンガ=智慧と慈悲の協会)の代表を務めている。
サンガ師は幼少期に来日し、堀澤師の下、比叡山で修行を積んだ。その後、インドに帰国し、ルヤード村で禅定林を主宰。布教活動を続ける一方、大乗仏教精神に基づく社会福祉活動を展開するPMS(パンニャ・メッタ・サンガ=智慧と慈悲の協会)の代表を務めている。PMSは、孤児院「パンニャ・メッタ子供の家」を中心に貧しい子供たちの生活安定のために支援を行うと共に、仏教的情操教育を施し将来の人材育成のための活動を行っている。また同時に、福祉・教育・医療など幅広い活動も続けている。
10周年を迎える大本堂は、天台宗開宗千二百年慶讃大法会の記念事業として、パンニャ・メッタ協会日本委員会(P・M・J 谷晃昭理事長)の支援の下、建立された。
全ての生命の平等を説く仏教。その発祥の地であるインドは、今なおカースト制度の壁は厚く、差別と貧困に苦しむ数多くの人々が暮らしている。差別の否定と生命の平等の教えをいかにインドに根付かせ得るかが、インド仏教再生の課題であった。
その精神的象徴としての威容を誇る大本堂建立から10年を経た現在、禅定林の活動は、確実に根を降ろしている。大本堂落慶時の大法要では約十万人が参集、昨年の9周年の法要には、インド各地からその倍の二十万人にも及ぶ仏教徒が随喜している。なお、老朽化した「パンニャ・メッタ子供の家」を近隣のナグプール市に新築移転、記念大法要が営まれる8日には、その竣工式も執り行われる。
「特別授戒会」も執り行う
サンガ師はかつて「大本堂をインド仏教の心の拠り所とし、伝教大師のみ教えのもと、未来に法を伝える仏弟子を養育していきたい」と大本堂建立の意義について語っていた。その意義の実践として今回の記念大法要では「特別授戒会」を叡南門主を伝戒大和上として執り行う。現地の仏教徒百名近くが戒を受ける予定である。
なお、授戒会を理解し易くするため、儀式中『懺悔文(さんげもん)』や『四弘誓願(しぐせいがん)』などの復唱は、ヒンディー語やパーリー語を交えて行われる。