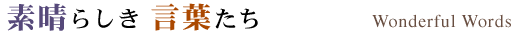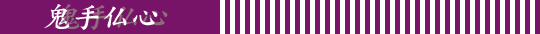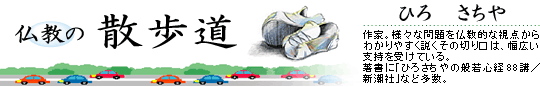第30回「世界宗教者平和の祈りの集い」アッシジ
イタリア・アッシジで第30回「世界宗教者平和の祈りの集い」が、9月18日から20日まで開催された。この集いは、カトリックの信徒団体である聖エジディオ共同体が主催するもので、天台宗は森川宏映天台座主猊下を名誉団長とする使節団を派遣、世界の宗教指導者と共に、世界平和への祈りを捧げた。祈りの集い参加にさきがけ、16日に、森川座主猊下はローマのバチカン(ローマ法王庁)を訪問。第266代ローマ教皇・フランシスコ聖下と会見し、明年比叡山で開催される「比叡山宗教サミット30周年記念『世界宗教者平和の祈りの集い』」への出席を懇請し、親書を手渡した。
 バチカンと日本天台宗との縁は、1981年にヨハネ・パウロ二世教皇が日本を訪問し日本の宗教指導者を前に「宗教協力には、天台宗宗祖最澄の示した『己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり』という精神が必要である」と述べたことに始まる。
バチカンと日本天台宗との縁は、1981年にヨハネ・パウロ二世教皇が日本を訪問し日本の宗教指導者を前に「宗教協力には、天台宗宗祖最澄の示した『己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり』という精神が必要である」と述べたことに始まる。1986年には世界の代表的宗教指導者がカトリックの聖地アッシジに招かれ「世界宗教者平和の祈りの集い」が開催された。その時天台宗からは第253世山田恵諦天台座主が参加した。以来、アッシジの祈りの集いの精神を引き継ぎ、比叡山宗教サミットが開催されてきている。比叡山での祈りの集いは今年で29周年を迎えた。
会見で森川座主は、フランシスコ教皇としばし歓談し、明年8月3、4日に開催される「比叡山宗教サミット30周年記念『世界宗教者祈りの集い』」への出席要請親書を手渡した。