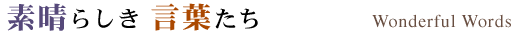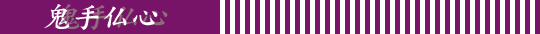7年ぶりに一隅を照らす運動推進大会
実践3つの柱で被災地支援継続
陸奥教区
一隅を照らす運動陸奥教区本部(千葉亮賢本部長)は9月5日、岩手県奥州市の前沢ふれあいセンターで「一隅を照らす運動岩手大会」を開催した。
コロナ禍により平成30年に仙台市で開かれて以来、7年振りの大会に約400人が参加。
一隅を照らす運動の精神を再確認し、東日本大震災をはじめ各被災地の早期復興と世界平和を願いともに祈りを捧げた。
 陸奥教区本部は3年毎に一隅を照らす運動推進大会を開いてきたが、令和2年頃から流行が始まった新型コロナウイルス感染症により開催中止を余儀なくされていた。
陸奥教区本部は3年毎に一隅を照らす運動推進大会を開いてきたが、令和2年頃から流行が始まった新型コロナウイルス感染症により開催中止を余儀なくされていた。実に7年ぶりの開催となった今大会には、教区全域より約400人が参加し、再会を喜び合った。
菅原光聴副本部長の開会の辞で開幕後、千葉本部長は「普段の生活の中にも一隅を照らす運動の精神を活かし、菩提寺の住職とともに活動してもらい生活に溶け込める運動を目指したい」と決意を述べた。
同教区出身で現在天台宗参務の四竃亮真法人部長は「一人ひとりが一隅を照らすことにより、社会が照らされていく。改めて一隅を照らす運動の精神を認識していただき、いっそう運動への協力を」と呼びかけた。
続いて「伝教大師報恩並びに災害復興祈念法要」を千葉本部長の導師で奉修。教区内住職ら出仕のもと、叡山講福聚教会陸奥地方本部の会員らによる御詠歌奉納とともに今も復興途上にある被災地の安寧を祈願した。
被災経験を
後世に繋ぐ
また第二部では、一隅を照らす運動広報大使の露の団姫師による落語、県沿岸部に伝わる郷土芸能の大槌城山虎舞の迫力ある演舞が大会に華を添えた。
今大会では、「災害・たすけあい・みとめあい」をテーマに座談会が開かれた。国難とも言われる東日本大震災から14年が経ち、被災地には徐々に活気が戻りつつある。
しかし国内外では災害が頻発し、いまだ戦争が絶えない状況が続く。多くの人びとが被災者となった同教区として、震災当時の様子を後世に伝える責任から座談会を企画した。
四竃法人部長、露の団姫師、天台仏教青年連盟前副代表の小林伯裕報恩寺住職、大槌城山虎舞のメンバーをパネリストに、菅野宏紹陸奥教区本部事務局長が進行した。
各者が体験した震災当時の様子やボランテイア活動に従事した経験談などが語られ「先祖らが繋いでくれた絆が有事の際に活きた」、「被災者への共感の気持ちが大切」などの意見が出された。また防災への豆知識なども紹介された。
菅野事務局長は「支援にも一隅を照らす運動の『生命・奉仕・共生』の実践3つの柱で成り立っていることを話しを聞いて改めて感じた。一人ひとりが出来うることから実践し、示すことで周りに広がることを願っている」とまとめた。
なお参加者からの浄財として約130万円が同総本部地球救援事務局に寄付された他、教区仏教青年会による募金活動も行われた。