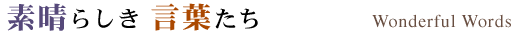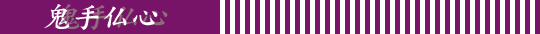「道心」をもって仏国土建設へ
- 藤光賢天台座主猊下が法燈をご継承 -
今冬2月1日に第259世天台座主にご上任された藤光賢探題大僧正の「傳燈相承式」が6月10日、比叡山延暦寺根本中堂にて厳かに執り行われた。
藤座主猊下は、本尊薬師如来のご宝前において『傳燈相承譜』に署名され、宗祖伝教大師より連綿と伝わってきた法燈を継承された。
同日午後からは、「傳燈相承祝賀会」が京都市内のホテルで開催され宗教界はじめ、政財界など各界から約600名の来賓が出席し、藤座主猊下のご上任を祝した
 傳燈相承式は天台宗最高の慶事とされる。
傳燈相承式は天台宗最高の慶事とされる。藤座主猊下が乗られた殿上輿は午前10時過ぎに控え所である大書院を出立。翠雨が延暦寺境内の新緑を一層輝かせる中、天台宗要職や延暦寺一山住職らの出仕僧を伴われて根本中堂までを進まれた。
入堂された藤座主猊下は、登壇・焼香後、荘厳な祝祷唄が堂内に響き渡るなか、『傳燈相承譜』にご署名された。(写真)
座主猊下の御心を旨に
傳燈相承譜は、第一世天台座主義真和尚から第258 世大樹孝啓前座主までの歴代座主が就任の証として署名されている座主血脈譜である。
根本中堂中陣には祭壇が設えられ、正面左に桓武天皇御真影、右に宗祖伝教大師御影を奉安。その宝前に、八舌の鑰、勅封の鍵、五鈷、鉄散杖、一字金輪秘仏などの伝教大師ゆかりの秘法具や大乗戒伝授に欠かせない仏舎利などが供えられ、新座主猊下に継承された。
そして滞りなく古式に則 った儀式を修された藤座主猊下は、天台座主として宗徒に『諭示』を発せられた。
この後、天台宗を代表し細野舜海宗務総長が「『道心』の志をもって仏国土の建設達成に邁進されますことを切に望みますとのお言葉を賜りました。私ども宗徒は、座主猊下の御心を旨とし、檀信徒の皆さまと共に仏国土建設に邁進すべく、心を新たにしております」と祝辞を述べた。