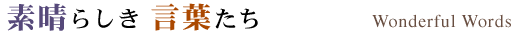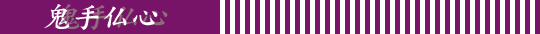増加する寺院の侵入盗被害
-防犯研修会で意識向上- 群馬教区
群馬教区(三浦祐俊宗務所長)は4月17日、教区内寺院において頻発している侵入盗被害を憂慮し、教区宗務所において緊急の「防犯研修会」を開催した。警察官や実際に被害にあった住職の講話などを通し、70名の参加者が防犯意識の向上に努めた。
 同研修会は、教区内寺院の安全・安心に資することを目的に、被害状況の共有・防犯意識の向上・具体的な防犯対策等を学習するために開催した。
同研修会は、教区内寺院の安全・安心に資することを目的に、被害状況の共有・防犯意識の向上・具体的な防犯対策等を学習するために開催した。近年、寺社を狙った窃盗は増加傾向にあり、警察庁が発表した20 22年に発生した神社仏閣の刑法犯件数は5千を超えている。
また群馬教区が実施したアンケート調査では、32カ寺が被害にあったという結果が出た。これらの現状から、2月中旬から研修会開催に向けて準備を開始。多方面から招いた講師の話に参加者らは熱心に耳を傾けた。
研修会開催にあたり三浦宗務所長は、「令和3年頃から寺院を狙った侵入盗事件が始まり、近年では巧妙な手口も増えている。私たちは、お預かりしている寺院の財産、そして寺族を守るためにも、防犯意識を一層高め、寺院の防犯対策を強化してまいりたい」と挨拶した。
研修会前半では、高崎警察署生活安全課、宗務副所長、教区議会議長による講義が行われた。
生活安全課署員は、過去の侵入盗事犯の情報をもとに、狙われやすい寺院の特徴や、犯人が嫌がる効果的な防犯対策等を紹介。もし犯人と対峙してしまった場合には、何よりも人命を最優先するよう強調した。
続いて眞木興空宗務副所長が、研修会開催に先立って実施された「教区被害状況調査」の結果を報告。教区内の一割を超える寺院が侵入盗被害にあっていることや、被害の多くに共通する侵入手段、発生時刻等が報告された。
また実際に侵入被害にあった林祐進教区議会議長(南前橋部光琳寺住職)からは、被害当時の具体的な様子が報告された。併せて部内複数寺院で同時多発的に発生した侵入盗事案を受け、LINEグループ等による早期の情報共有と、教区宗務所への被害報告の必要性が語られた。
研修会後半では、天台宗災害補償制度の村上憲一郎氏から、盗難被害補償に関する説明、並びに民間警備会社2社による、デモンストレーションを含む具体的な防犯警備システムの紹介も行われた。
多岐にわたる講義内容により同研修会は、参加者各位が自坊の安全に向けて多くの情報を得る有意義なものとなった。 (報告=大沢亮智通信員)