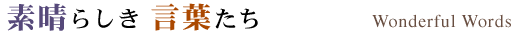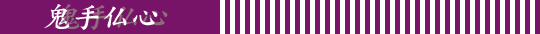第38回 世界宗教者平和の祈りの集い フランス・パリ
「平和を想像する」をテーマに諸宗教代表者らが対話
 「世界宗教者平和の祈りの集い」は、1986年に当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ二世聖下の呼びかけによりイタリア・アッシジで始められたもので、以来、ヨーロッパで都市を変えながら年一度開かれている。
「世界宗教者平和の祈りの集い」は、1986年に当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ二世聖下の呼びかけによりイタリア・アッシジで始められたもので、以来、ヨーロッパで都市を変えながら年一度開かれている。小堀名誉団長と大澤団長のほか、天台宗からは岩田真亮天台宗参務・教学部長と青木円学延暦寺副執行・管理部長が副団長として参加した。
エジディオ共同体創設者のアンドレア・リッカルディ教授が集いの歴史を振り返った上で、今大会の開催意義を強調。また、フランスのマクロン大統領やパリのアンヌ・イダルゴ市長らがスピーチし、世界で起こる諸問題解決に向けた宗教者の議論に期待を寄せた。
23、24日は、パリ中心部の各会場で21の分科会が行われ、その一つで小堀名誉団長は「偉大なるアジア 宗教の課題」と題して講演した。
小堀名誉団長は「あらゆる宗教が混在するアジアには、多様性こそが価値と魅力であり大変重要な点である」と述べ、経済発展が著しい反面、いまだアジア全体で6億人以上が貧困問題に直面していると指摘。
そして伝教大師の『忘己利他』を紹介し「たとえ戦争がなくても、貧困や差別、人権侵害がはびこる社会は平和とは言えない」と訴え、「ひとつの価値観や正義だけで縛るのではなく、他を認め尊重し合う、これこそがそれぞれの命を尊ぶことであり、この集いの趣旨とも響き合うものであると確信している。個々の宗教、個々の文化を尊重し合い、助け合う。アジアはこれからそのことに向かわなくてはならない」と方向性を示した。
最終日の夕刻には、各宗教・宗派による平和の祈り法要が市内各所で営まれ、日本仏教世界平和祈願法要を小堀名誉団長の導師のもと奉修。続く閉会式では「平和宣言文」が採択され全日程を終えた。
令和6年能登半島地震、またこの度の令和6年9月能登半島豪雨により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。皆様の心の平安と、一日も早く日常が戻ることを願い、天台宗は支援を継続してまいります。
天 台 宗
一隅を照らす運動総本部