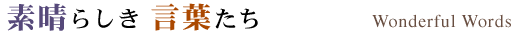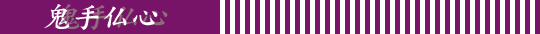-比叡山宗教サミット37周年-
「世界平和祈りの集い」8月4日に開催
 比叡山宗教サミット37周年「世界平和祈りの集い」が8月4日、比叡山上で開催される。日本全国から宗教者が集い対話し、それぞれの儀礼を尊重し合いながら心をひとつに世界平和への祈りを捧げる。
比叡山宗教サミット37周年「世界平和祈りの集い」が8月4日、比叡山上で開催される。日本全国から宗教者が集い対話し、それぞれの儀礼を尊重し合いながら心をひとつに世界平和への祈りを捧げる。比叡山宗教サミット「世界宗教者平和の祈りの集い」は、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の提唱によりイタリア・アッシジで開かれた「世界平和の祈り集会」の精神を引き継ぎ、昭和62年(1987)に開催。以来、周年記念行事を毎年実施し、世界各地の諸宗教者らが恒久平和実現のための使命と責務を語り合ってきた。
従来屋外で執り行っていた式典は、昨年から屋内外の2部構成での開催となり、本年は延暦寺会館にて13時から開会される。
「平和の力を信じ −中村先生の意志を継いで−」と題して、ペシャワール会PMS(ピースジャパン・メディカル・サービス)支援室室長の藤田千代子氏が、故中村哲医師と共に尽力したパキスタンやアフガニスタンでの平和医療活動について講演。また昨年同様にSDGsの観点から、記念品の代わりに制作費相当の浄財を日本ユニセフ協会に寄託する。
一隅を照らす会館前「祈りの広場」では、サミットで採択された比叡山メッセージを朗読し、平和の鐘を鐘打して各宗教者が黙祷で祈りを捧げる。主催者代表の大樹孝啓天台座主猊下が“お言葉”を述べられ、海外からの平和のメッセージが披露される。
15時20分頃から屋外で行われる「平和の祈り」は、オンラインでライブ配信される予定。プログラムの詳細は左記の通り。(4面に関連記事)
令和6年8月4日㈰ 13:00開式
平和の式典(屋内)
13:00 開式
13:05 平和を語る(藤田氏講演)
14:20 ユニセフ支援金寄託式
平和の祈り(屋外)
15:20 比叡山メッセージ朗読
15:30 平和の鐘・平和の祈り
15:35 海外からの平和のメッセージ披露
閉式
詳細は 天台宗公式ホームページ http://www.tendai.or.jp
動画配信サイトYouTubeにて同時配信 配信時間/15:10~