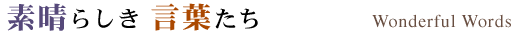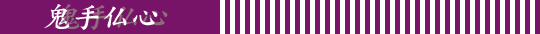熊本地震三回忌追悼法要を営む
平成28年4月14日に発生した熊本地震は、熊本県、大分県を中心に大きな被害をもたらし、天台宗の寺院、檀信徒も少なからぬ被害を受けた。発生から2年を過ぎた本年4月22日、九州西教区では熊本県八代市の釈迦院 (作村尚範住職)において「熊本地震物故者三回忌 並 復興祈願法要」を営み、参列者約120名が犠牲者の慰霊と早期復興を祈った。
 「熊本地震物故者三回忌 並 復興祈願法要」は、22日11時より釈迦院で嘉瀬慶文宗務所長を導師に、教区内寺院住職の出仕で執り行われた。法要には、被災寺院住職、檀信徒、甘井亮淳天台宗財務部長、藤光俊天台宗宗議会議員、今泉好正教区議会議長らとともに、被災地益城町の仮設住宅に暮らす被災住民の人々も多数参列した。法要最後には、参列者に大般若による加持が行われたほか、甘井財務部長より被災地の自治体、町作りのための民間団体に義援金と協賛金が贈呈された。
「熊本地震物故者三回忌 並 復興祈願法要」は、22日11時より釈迦院で嘉瀬慶文宗務所長を導師に、教区内寺院住職の出仕で執り行われた。法要には、被災寺院住職、檀信徒、甘井亮淳天台宗財務部長、藤光俊天台宗宗議会議員、今泉好正教区議会議長らとともに、被災地益城町の仮設住宅に暮らす被災住民の人々も多数参列した。法要最後には、参列者に大般若による加持が行われたほか、甘井財務部長より被災地の自治体、町作りのための民間団体に義援金と協賛金が贈呈された。法要後、導師を勤めた嘉瀬宗務所長が「地震で亡くなられた方々の三回忌法要を営まさせていただきました。被災直後の支援活動に続いて、仮設にお住まいの方々の支援など、できる限りの支援を続けて参りました。一日も早い復興を目指し、教区としても頑張っていきたい」と挨拶。また、仮設住宅の被災住民も「今日の法要で、新たに悲しみがわき起こりましたが、犠牲者の回向ができて良かった。まだまだ元の暮らしを取り戻せていませんが、頑張って生きたいと思います」と語っていた。
熊本地震から2年経った2018年の時点でも、未だ避難指示が2市1町1村、約1400世帯に出ており、避難勧告も1市5町1村、約3万世帯に出されている。避難所は今も被災各県で1000ヵ所以上あり、仮設住宅に暮らす人も3万人を超える。また避難者は11万人以上に上るといわれている。
被災から2年という時間が経過した現在は、炊き出し、後片付けなど被災直後の支援活動と違った活動が求められる。被災者の生活環境が変わったことによる孤立化、引きこもりが増えてくることが懸念される。今後は、被災者ひとり一人の日常生活を支える持続的な福祉活動が必要となる。天台宗としても、その視点からの支援活動を考えていく時期となっている。