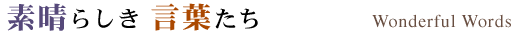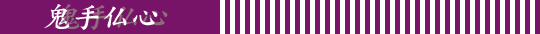「六郷満山峯入」行を厳修
明年の開山1300年を前に 大分国東半島・六郷満山会
神仏習合の郷、大分県国東半島にある天台宗寺院で構成する六郷満山会(松本量文会長・長安寺住職)は平成30年に六郷満山開山1300年を迎えるのを記念し、4月2~30日に亘り「六郷満山峯入」行を厳修した。険しい山や谷を踏破する荒行に、大先達の河野英信富貴寺住職、先達の隈井修道行入寺住職を先頭に天台僧21名が参加。今回は記録を頼りに164年ぶりに再興した183カ所の旧霊場を巡り、六郷満山の開祖・仁聞菩薩(にんもんぼさつ)への報恩心を示し、祥当年への決意を新たにした。
 峯入は、仁聞菩薩が厳しい六郷二十八谷を回峰し修行した霊跡を巡拝する行で、斉衡二(855)年に仁聞菩薩から国東半島巡礼の峯道を授けられた僧・能行により始められたとされる。
峯入は、仁聞菩薩が厳しい六郷二十八谷を回峰し修行した霊跡を巡拝する行で、斉衡二(855)年に仁聞菩薩から国東半島巡礼の峯道を授けられた僧・能行により始められたとされる。その後、復興・中断を経て嘉永六(1853)年を最後に中絶していたが、昭和三十四(1959)年、百六年ぶりに再興された。
昭和五十四年から、十年毎に行われており近年では平成二十二年に奉修されている。今回は開山一千三百年を記念した行として、初日と結願(けちがん)のみ一般参拝者に開放した。その他の日程中は、僧侶のみ参加の非公開で修行された。
初日は宇佐神宮で初日神事と採燈護摩供、30日の結願は両子寺(ふたごじ)(寺田豪明住職)で採燈護摩供が河野富貴寺住職を大導師に厳修された。(写真)
結願の採燈護摩供では、寄せられた多くの護摩木を焚き上げ、出仕僧侶らが人々の所願成就などを祈り、満行への感謝と各記念事業の成功を祈願した。最後に参拝者にお加持を授けた。河野住職は「九州国立博物館で特別展が開かれるなど、来年に向け様々な企画が予定されている。是非足を運んでほしい」と参拝者に呼びかけた。
国東の人々は野仏や磨崖仏を日々供養してきた。古より変わらない信仰が今も息づく。
183カ所の霊場巡拝再興は、満山会関係者にとっても、その風土を後世に伝えたいとの願いからだった。
その再興に尽力した一人が先達を勤めた隈井行入寺住職。前回(平成二十二年)初入峯(にゅうぶ)への心構えとして文献を調べ始めたのをきっかけに、平成二十一年から四年かけて調査・研究を重ねてきた。
明年へは「一般の方々にも知っていただくと共に、私たちも精進を重ねたい」と意気込んでいる。松本六郷満山会会長も「復興は我々の悲願だった。来年へ弾みをつけた」と喜んだ。
九州東教区では、この勝縁を祖師先徳鑽仰大法会の報恩事業として位置づけている。 座主猊下による宇佐神宮での法華八講や特別授戒会、一般には九州国立博物館での特別展、様々な催しを開くなど、幅広く一般に周知する意向だ。
開山一千三百年実行委員長を勤める秋吉文隆宗務所長は「この勝縁に出逢えたことに感謝したい。伝教大師御遠忌を見据え、地方でも宗祖ゆかりの諸行事があれば教区の事業として取り組みたいと考えていた。明年に向けて、大法会事務局とも連携を密にし、準備していきたい」と話している。