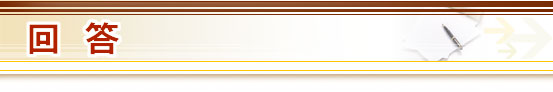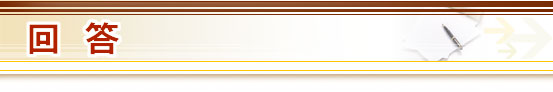|
戒名というと、人が亡くなってから授かるものと思われている方が多いと思いますが、本来はそうではありません。仏教に帰依し、仏様の弟子として、その教えにしたがって戒を守る誓いをたてた者に与えられる名前が戒名です。
戒とは、仏教徒が守るべき「いましめ」のことで、立場に応じて様々な種類の戒があり、出家者と在家者の間でも異なります。例えば在家者であれば、三帰五戒や八斎戒があります。ここでは在家・出家に共通の大乗菩薩戒の基本となる「十善戒」(じゅうぜんかい)を紹介します。
- 不殺生(ふせっしょう)いきものを殺さない
- 不偸盗(ふちゅうとう)他人のものを盗まない
- 不邪婬(ふじゃいん)淫らな男女関係をむすばない
- 不妄語(ふもうご)うそをつかない
- 不両舌(ふりょうぜつ)二枚舌で仲違いさせない
- 不悪口(ふあくく)悪口をいわない
- 不綺語(ふきご)うわべだけの言葉をいわない
- 不貪欲(ふとんよく)むさぼり求めない
- 不瞋恚(ふしんに)怒らない
- 不邪見(ふじゃけん)間違った見方でものごとを判断しない
このような戒は、仏門に入るときに受戒会という儀式によって授かりますが、その際に俗名とは別に新たに与えられるのが戒名です。キリスト教徒が洗礼を受けたときにクリスチャンネームをもらうのと似ています。
したがって、戒名は本来ならば生きているうちにいただくものであり、日本でも古くは天皇や公家をはじめ上流公家や上流武家の間で、生前に受戒して戒名を持つことが流行しました。しかし、その目的は必ずしも純粋な信仰心によるだけではなく、息災や長寿などの現世利益を期待する側面もあったようです。
やがて、このような上流階級の戒名授与も形骸化すると、臨終間際や亡くなった後になってあわてて僧侶を招いて受戒して戒名をもらうという、いささか本末転倒な事例も目立つようになります。ここに葬儀と戒名授与が結びつく原点があるといえます。
さらに時代が下って江戸時代になると、幕府の政策として、キリシタンでないことを証明するために庶民一人一人を寺院に登録させる檀家制度が進められ、寺院は戸籍係のような役目を担うようになりました。その際に、死者がキリシタンでないことの証しとして戒名をつけることが義務付けられました。その結果、死後戒名は上流階級に限らず、庶民にまで普及するに到ったのです。
ここで死後に授けられる戒名を決して否定するわけではありません。死後に授けられる戒名は、人生の最期に仏縁を結ぶ大切なご縁といえます。しかし、できれば生きているうちに受戒をして、仏弟子としてより良い人生をおくっていただきたいと思います。
最近では、「長生きができます」「高額な戒名料を支払わなくてもいいです」「どの宗派の戒名でもお付けします」と、生前戒名を勧誘している団体などがありますが、仏弟子となって生きるという生前戒名の意味をよくご理解していただきたいと思います。
天台宗では、総授戒運動を推進しています。皆様がご参加できる円頓受戒(えんどんじゅかい)や結縁潅頂(けちえんかんじょう)という授戒会(じゅかいえ)や仏縁を結ぶ儀式が開催されています。まずは菩提寺にご相談ください。
|