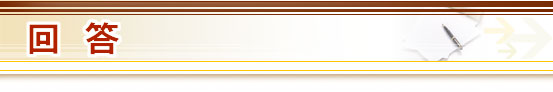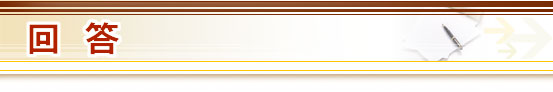|
「追善」とは、先に亡くなった親・兄弟・先祖の御霊のために、生きている者が追って善行を積み、その冥福を祈ることをいいます。具体的には、仏壇やお墓へお参りすることはもとより、亡者の年忌などに法事を営んで供養するので、「追善供養」というわけです。
法事では、仏様やご先祖様に対してお花やお香やお供物をお供えし、菩提寺の僧侶に読経していただきます。また法事に集まった人々に飲食を提供し、故人を偲びつつ近況を語り合います。これら法事において施すのもの全てが供養なのです。
また、供養を次のような視点で考えるとわかりやすいでしょう。
- 香華・飲食物をお供えする。
- ご先祖様を偲び敬う心を養う。
- 仏縁を受けとめて修行・回向する。
つまり、この3つの要素が法事にあります。ご先祖様の菩提を願うと共に、法事は自己の善徳を積む修養の場でもあります。
法事の終わりには『回向文』(えこうもん)というお経が唱えられます。
「願わくばこの功徳をもって遍く一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道を成ぜん」
回向とは、自らが修めた善行の功徳をめぐらして、他の衆生に差し向けることをいいます。追善供養たる法事を営むことで、ご先祖様や有緑無縁の諸霊、周囲のすべての人たちに功徳が及び、そしてすべての人と共に仏道を完成したいと願います。
人間は、自分と自分を取り巻く多くの方々と相互に助け合い、譲り合い、関わりあって生かされて生きています。しかし、複雑多忙な現代社会にあっては、普段の生活において自己をみつめて反省したり、将来についてゆっくり考えたり、周囲に感謝する余裕があまりないのではないでしょうか。
ですから、せめてご先祖様の年忌を節目として法事を営み、機会をみつけて寺院行事に参加し、ご先祖様に対して心からの供養をしたいものです。
仏壇の前で手を合わせる時、墓参で香華を手向けて合掌する時、法事に参列する時、不思議と心が落ち着き、安心(あんじん)が得られます。このことは仏教徒が修する仏事の功徳なのではないでしょうか。
ご先祖様は、いつでもあなたとの心の対話を待っていらっしゃいます。
|