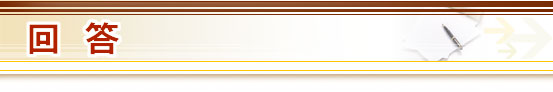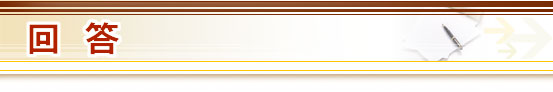|
仏壇とは、仏像やお位牌を安置する場所をいいます。その起源については諸説があり、定かではありませんが、通説では『日本書紀』に、白鳳14年(685年)3月27日、天武天皇が「諸国の家ごとに仏舎を作り、即ち仏像と経とを置きて礼拝供養せよ」との勅命を出したのがはじまりとされています。また、貴族や上流階級の人々が屋敷内に建てた持仏堂(じぶつどう)が小型化されて屋内に取り込まれたとする説や、お盆の魂棚(たまだな)を起源とする説もあります。江戸時代になると一般庶民の間にも広く普及したようです。
仏壇の位置については様々なしきたりがいわれていますが、余りこだわりすぎる必要はありません。大切なのは仏様やご先祖様に日々の感謝をすることです。ですから、毎日お参りをして、お茶やご飯をお供えしやすく、家族がよく集まるような場所を選ぶのがよいでしょう。また、直射日光が当たるところ、湿気が多く風通しのよくないところ、目が届かず火の始末がしにくいところは避けたほうがいいでしょう。
次に同じ仏壇に他姓のお位牌を祀ることですが、そもそも仏壇は本尊を祀る場所であり、ご先祖様は仏弟子として法名や戒名がつけられています。仏様の世界では誰もが平等ですから、生前の姓が異なっても何の支障もありません。また最近では、少子化・都市化・核家族化によって新しいスタイルとして合祀墓・納骨堂が注目を浴びています。合祀墓は自分の意志で他人と一緒に納骨されるお墓です。これは私たち一人一人が仏弟子であり平等であるとの思想から生まれたものだとも言えます。よって、お参りする側も姓の違いにこだわることなくお参りすべきでしょう。
|