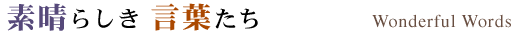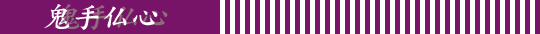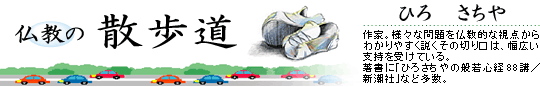慈覚大師1150年遠忌等を厳修へ
―平成24年度から10年にわたり順次奉修―
祖師先徳顕彰大法会企画委員会(阿純孝委員長)では、昨年十二月十四日に同企画委員会を開催し、平成二十四年四月一日から平成三十四年三月末日までの十年間にわたり慈覚大師一一五〇年遠忌をはじめとする大法会を行うことを決定した。
 今回の大法会は、平成二十五年が慈覚大師の遠忌に相当することから企画された。
今回の大法会は、平成二十五年が慈覚大師の遠忌に相当することから企画された。十年にわたり順次、慈覚大師一一五〇年遠忌、伝教大師御生誕一二五〇年、一二〇〇年大遠忌、恵心僧都一〇〇〇年遠忌と続く。
各祖師先徳を顕彰すると共に、その教えと信仰を現代に布衍させることが目的。具体的な記念行事等は、二月八日に行われる同企画委員会から協議される。
大法会のトップに奉修される慈覚大師円仁は、現在の栃木県下都賀郡岩舟町あたりで生まれたとされる。幼少の頃に伝教大師と出会う夢を見て、比叡山に登り伝教大師に師事し、伝教大師の東国巡礼につき従っている。
伝教大師入寂後は、比叡山の指導者となり、伝教大師が生前訪れることができなかった東北地方にも巡錫し布教活動を行った。
その過労がたたったのか、四十歳で比叡山の横川で療養している時に、夢の中で伝教大師が「中国で仏教を学んで来て欲しい」と頼んだのをきっかけに遣唐請益僧として中国に渡ることを決意する。
八三八年、三度目の渡航でようやく中国に渡った慈覚大師は、何度も天台山へ行くことを願い出るが、なかなか許可が下りない。やむなく揚州で経典を収集する。その数は一九八巻に及んだ。
帰国船に乗り込んだものの、何としても仏教を学んでから帰国したいと思い、紆余曲折を経て、山東半島の赤山付近で船が立ち往生した時に急遽下船する。そこで、慈覚大師は赤山法華院の僧から、五台山でも天台が盛行されていることを聞き、五台山に向かうことを決意。
赤山から五台山まで千二百キロの道程を経て到着。更に同じぐらいの道のりを長安へと向かったのである。長安では密教の勉強と経典書写に力を注ぎ、目的は達成された。
しかし、当時道教を信奉する唐の皇帝・武帝は仏教に厳しい弾圧(会昌の破仏)を加えたため、還俗を強制され、長安を追放される。
後、八四六年に武帝が急逝したために慈覚大師は僧に戻り翌年に帰国する。この経緯は、慈覚大師が著した世界三大旅行記といわれる「入唐求法巡礼行記」に詳しい。
経典の他に慈覚大師が日本仏教にもたらした「声明」は、天台声明として完成し邦楽の源流となっている。八五四年に、慈覚大師は第三代天台座主となり、十年後に七十一歳で波瀾に満ちた生涯を閉じている。その二年後に、朝廷より、師の伝教大師の大師号と共に慈覚大師という大師号が下賜された。
これは我が国における初めての大師号の下賜であった。
…………………………………………………………………………
「祖師の教えを現代に」 阿純孝委員長
「武力によって国は滅びるのではなく、伝統を蔑(ないがし)ろにすることで国は滅びる」とは、ある哲学者の言だが、それは宗教にも言えることである。
宗教の本質は「教え」にあるのだが、その教えは歴史を背負いつつ、それを超え未来に向かっている。根本中堂の不滅の法灯の精神はまさにそれだ。
この大法会では、祖師先徳の教えを弘めることで、人々の心に法の灯をとどけたい。